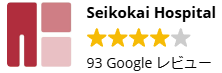「最近、胸がドキドキすることがある」「なんとなく息苦しい気がする」「ふとした瞬間に鼓動が乱れる感じがある」、そんな症状を感じたことはありませんか?
日常生活で、ストレスや疲れ、カフェインの摂取などによって一時的に心拍数が乱れることは珍しくありません。ただし、その“乱れ”が続いたり、日常生活に支障が出るようであれば、「不整脈」が関係しているかもしれません。
今回は、不整脈の原因やサインについて、また放置するとどんな影響があるのかをわかりやすくご紹介します。さらに、不整脈を見逃さず、しっかりと捉えるために役立つ「ホルター心電図」という検査についてもお話しします。
ちょっとした違和感でも、無理せず立ち止まってみることが大切です。「最近、自分の体はどうかな?」と、ふと考えるきっかけとして、ぜひ最後までお読みください。
不整脈とは?
心臓は、全身に血液を送り出すポンプのような役割を担っており、酸素や栄養を体の隅々まで届けるために、一定のリズムで拍動しています。安静時の心拍数は1分間に60〜100回程度が目安とされ、このリズムが規則正しく保たれることが健康な状態と言えます。
不整脈とは、この心臓のリズム(脈拍)が「速すぎる」「遅すぎる」「不規則になる」といったように乱れてしまっている状態を指します。
どうして不整脈が起こるの?
不整脈は、さまざまな理由で心臓の電気信号がうまく伝わらなくなることで起こります。
健康な方でも一時的に起こることがありますが、年齢を重ねることで心臓の働きや電気の流れが変化したり、ストレスや疲労、睡眠不足によって自律神経のバランスが乱れたりすると、心拍が不安定になることがあります。
また、カフェインやアルコールの摂り過ぎ、ナトリウムやカリウムなどのミネラルバランスの乱れも心臓のリズムに影響を与えます。他にも、高血圧や心臓の病気、甲状腺の異常などが背景にある場合や、服用中の薬が原因となっている場合など、不整脈の原因は一つではなく、複数の要因が重なって起こることもあります。
「ちょっと疲れているだけかな」と思っていても、実は心臓がSOSを出しているサインかもしれません。
主なタイプと特徴
- 脈が速くなる「頻脈性不整脈」
心拍数が1分間に100回以上になる状態で、動悸や胸の不快感、めまいを感じることがあります。代表的なものに心房細動や上室性頻拍があります。 - 脈が遅くなる「徐脈性不整脈」
心拍数が1分間に60回以下に落ち込む状態で、疲れやすさやふらつき、失神などを引き起こすことがあります。 - 脈が飛ぶ・リズムがバラバラになる「期外収縮」
健康な方にも起こることがあり、自覚症状がなければ特に治療は不要なケースも多いですが、頻度が高かったり症状が強い場合には検査が必要です。
不整脈のサイン、見逃していませんか?
不整脈は、軽度であれば気づかずに経過していることもありますが、次のような症状がある場合には注意が必要です。
✅急に胸がドキドキする(動悸)
✅脈が飛ぶように感じる
✅息切れや疲れやすさを感じる
✅立ちくらみやめまいがある
✅失神したことがある
✅血圧が急に下がったことがある
特に高血圧、糖尿病、心臓病の既往がある方や、高齢の方は不整脈が重症化するリスクが高いため、早めの受診をおすすめします。
放置のリスクとその影響

不整脈をそのままにしていると、心臓のポンプ機能が低下し、全身に酸素や栄養が行き渡りにくくなることで、体のだるさや疲れやすさなどを感じるようになります。
特に「心房細動」では、心臓内に血液が滞って血栓ができやすくなり、脳卒中(脳梗塞)のリスクが高まります。
さらに、不整脈を長く放置すると、心臓に過度な負担がかかり続け、心不全を引き起こすこともあります。重度の不整脈(心室細動など)は、心臓が正常に動かなくなり、迅速な処置が必要になるなど命に関わるケースもあります。
また、不整脈が頻繁に起こると、動悸や息切れ、めまい、立ちくらみといった症状が日常的に続き、仕事や家事に集中できず、普段の生活に支障をきたすこともあります。
日常生活の中で心臓の動きを記録~ホルター心電図とは?
不整脈は“発作的”に現れることが多いため、病院で行う数十秒〜数分間の通常の心電図検査では、そのタイミングを捉えられないことも少なくありません。そのため、症状が現れているときの心電図を記録することが重要です。
そこで活用されるのが「ホルター心電図」です。これは、コンパクトな機器を体に装着して、24時間心臓の動きを記録する検査です。食事や仕事、外出など、普段どおりの生活を送りながら検査を受けられるため、日常生活の中で一時的に現れる不整脈のサインを見逃さずに捉えることができます。
これらの症状がある方は要チェック
日常生活に近い状態で心電図を記録できるホルター心電図は、以下のような症状に対して非常に有効です。
- 動悸や息切れが時々あるけれど、心電図検査では異常なしと言われた方
- 一瞬クラッとするようなめまいがある方
- 検診などで「脈が乱れている」と指摘を受けた方
- 一日の中で何度か動悸を感じる方
- 夜間や明け方に胸の不快感が現れる方
さらに、動悸や息切れといった症状が週に何度も繰り返し起こる、症状は軽いが数週間にわたって続いている、仕事や家事の合間に何度も息切れや胸の不快感を感じるなど日常生活に支障をきたしている場合には、早めの受診を検討することをおすすめします。
ホルター心電図検査の流れとポイント
検査中は痛みを感じることはなく、装着もシンプルで特別な準備はほとんど必要ありません。ただし、機器装着中はシャワーや入浴ができませんので、事前に済ませておく必要があります。また、肌が敏感な方は、電極を貼ることでかぶれが出ることがあります。
装着後は普段通りの生活を送り、翌日に機器を取り外します。その後、記録されたデータを解析し、不整脈の有無や種類、頻度などを詳しくチェックします。より正確な診断につなげるため、検査中に感じた症状や行動は「行動記録表」に記入しておくと良いでしょう。
検査結果に基づく治療
ホルター心電図検査で不整脈や心拍数の異常などが見つかった場合は、結果に応じた治療を進めていきます。
- 薬物療法
異常なリズムを整えるための薬(抗不整脈薬や心拍数をコントロールする薬)を使用します。症状や心臓の状態に応じて、薬の種類や量を調整していきます。 - 追加検査
さらに詳しい検査が必要な場合には、心臓の血管や電気の流れを詳しく調べるために、心臓カテーテル検査や電気生理学的検査が行われることがあります。
また、必要に応じて高度な治療(カテーテルアブレーション治療など)が選択されることもあります。これらの検査や治療は、症状や心臓の状態に応じて適切に検討されます。 - 経過観察
症状が軽い場合や、すぐに治療介入が必要ないと判断される場合は、一定期間ごとに心電図検査や診察を行い、変化がないかを慎重に見守ります。その際は、医師がより的確に判断できるよう、日常生活での症状記録をつけておくとよいでしょう。
また、検査結果に大きな異常が見られなかった場合でも、症状が完全に消えていない方や、今後のリスクを下げるために、生活習慣改善のアドバイス(例:適度な運動、バランスの良い食事、禁煙など)や、定期的な検査を受けることをお勧めします。特に加齢や生活環境の変化により心臓の状態は変わることがあるため、不整脈の再発や症状の改善具合を確認することが重要です。
まとめ:心臓のサイン、早めのチェックで安心を

「ドキドキするけど、疲れやストレスのせいかな」「病院で診てもらっても何も出なかったし…」——そんなふうに様子を見ているうちに、不整脈が見逃されてしまうこともあります。症状があっても日常生活に支障がないと、「まあ大丈夫かな」と受診を後回しにしてしまいがちですが、心房細動などの不整脈は、放っておくと脳梗塞や心不全の原因になることもあります。気になるサインがあれば、早めに医療機関を受診しましょう。
当院でも、内科医による診察と、必要に応じたホルター心電図検査を行っておりますので、気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。
早めの受診が、ご自身の健康を守る第一歩になります。