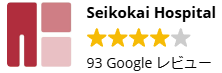近年、日本では高齢化が進み、認知症予防が社会的にもますます重要な課題となっています。そのような背景から、認知症リスクを少しでも減らすための新たな手段に関心が高まっています。
そんな中、最近の研究で「帯状疱疹ワクチンが認知症のリスクを軽減する可能性がある」という興味深い報告が発表され、医療関係者だけでなく、多くの方から注目を集めています。
実際、海外で行われた大規模な疫学研究では、帯状疱疹ワクチンを接種した人は接種していない人に比べ、後年に認知症を発症するリスクが低かったというデータが示され、話題となりました。
今回は、この注目の『帯状疱疹ワクチン』と『認知症予防』の関係について、最新の研究からわかるポイントやその理由、さらに私たちが今できる予防策について、わかりやすく解説します。
帯状疱疹が認知症リスクに関わる理由
近年、認知症は単なる加齢による脳機能低下だけでなく、慢性的な炎症や神経へのダメージといった要因がそのリスクに影響することがわかってきています。その一因として注目されているのが帯状疱疹です。
帯状疱疹は、子どもの頃に感染した水ぼうそうのウイルス(水痘・帯状疱疹ウイルス)が体内に潜伏し、年齢を重ねて免疫力が弱まったときに再び活動を始めることで発症する病気です。主に50歳以上の方に多く見られ、皮膚の痛みや発疹だけでなく、神経にも強いダメージを与えることがあります。その代表的な後遺症である帯状疱疹後神経痛は、発疹が消えた後も長期間にわたり痛みが残る状態で、神経への影響が深刻であることがわかっています。
さらに、このウイルスの再活性化に伴う慢性的な炎症や神経細胞へのダメージは、脳の認知機能に影響する可能性が指摘されています。特に免疫力が低下しやすい高齢者では、その影響が蓄積することで、記憶力や判断力の低下といった認知症リスクが高まると考えられています。
こうした背景から、帯状疱疹ワクチンによってウイルスの再活性化を防ぎ、脳や神経への負担を減らすことが、認知症予防につながる可能性が期待されており、その関連に大きな関心が集まっています。
帯状疱疹と認知症リスクをつなぐメカニズムとワクチンの役割
 帯状疱疹の原因ウイルスは神経節に潜伏し、免疫力が低下すると再び活動を始めます。この再活性化によって引き起こされる炎症反応は、神経細胞や血管にダメージを与え、慢性的な炎症状態を引き起こすことがわかっています。
帯状疱疹の原因ウイルスは神経節に潜伏し、免疫力が低下すると再び活動を始めます。この再活性化によって引き起こされる炎症反応は、神経細胞や血管にダメージを与え、慢性的な炎症状態を引き起こすことがわかっています。
こうした慢性炎症は、脳にとって大きなリスク要因であり、アルツハイマー病に特徴的なアミロイドβやタウ蛋白質の蓄積を促進する可能性が指摘されています。
さらに、神経ネットワークの破壊やシナプス機能の低下を引き起こし、結果的に記憶力や判断力の低下といった認知機能障害に繋がります。つまり、帯状疱疹ウイルスの再活性化による炎症が、脳内環境の悪化を促し、認知症発症のリスクを高めるメカニズムと考えられているのです。
帯状疱疹ワクチンは、この再活性化を防ぐことで慢性的な炎症を軽減し、神経細胞のダメージを抑制する役割が期待されています。加えて、ワクチン接種による免疫機能の維持は、加齢に伴う免疫力低下に対するサポートとなり、脳の健康を守る上でも重要な役割を果たすと期待されています。
このように、帯状疱疹ワクチン接種は、免疫機能の維持と慢性炎症の抑制を通じて脳への負担を減らし、認知機能を守る手助けになる可能性があるのです。
最新の研究から見えてきた帯状疱疹ワクチンの可能性
2020年代に入ってから、帯状疱疹ワクチンが認知症リスクを軽減する可能性を示す大規模な疫学研究が相次ぎ、注目されています。
たとえば、イギリスで行われた調査(Nature誌、2025年4月)では、生ワクチン(ゾスタバックス)を接種した70歳以上の高齢者において、7年後に新規認知症と診断される割合が約20%低下していたと報告されています。また、不活化ワクチン(シングリックス)に関する別の調査でも、認知症診断が平均で約164日遅れることが示されました。
これまで、帯状疱疹とその後遺症の予防に用いられてきたワクチンですが、こうした研究成果により、認知症リスクの軽減にも役立つ可能性が示され、予防医療としての意義が高まっています。
特に高齢者の健康管理においては、こうした最新の知見を踏まえ、適切な予防策を検討することがますます重要となるでしょう。
ただし、これらの研究はまだ初期段階であり、帯状疱疹ワクチンによる認知症予防効果をさらに確実に裏付けるには、今後も長期にわたる追加検証が必要です。それでもなお、従来の帯状疱疹予防に加えて、脳の健康維持に貢献するという新たな可能性として、ますます注目が集まっています。
ワクチンと生活習慣で認知症リスクに備えよう
 帯状疱疹ワクチンは新たな可能性を示していますが、それだけでなく、日々の生活でできる予防策も、認知症リスクの低減にはとても大切です。
帯状疱疹ワクチンは新たな可能性を示していますが、それだけでなく、日々の生活でできる予防策も、認知症リスクの低減にはとても大切です。
適切な生活習慣は、脳細胞がダメージを受けにくい環境を整え、記憶や思考の力を長く保つ手助けになります。
例えば、適度な運動は脳への血流を増やし、新たな神経細胞の成長を促します。ウォーキングや体操、軽い筋トレなど、無理のない範囲で体を動かすことから始めるとよいでしょう。
また、バランスのとれた食生活も大切です。野菜や果物、魚、ナッツ類に含まれるビタミンやオメガ3脂肪酸は、脳を酸化ストレスから守り、神経細胞の健康を支えます。
さらに、十分な睡眠には脳内の老廃物を排出する作用があり、記憶を整理する働きもあります。そして、社会交流や趣味活動は認知機能を活性化させることがさまざまな研究から示されています。家族や友人と話す機会を増やしたり、新しいことに挑戦したりすることで、脳に適度な刺激を与えられます。
こうした生活習慣と帯状疱疹ワクチンをうまく組み合わせることで、免疫面と生活面の両方から脳への負担を減らすことができます。
「今できることから一歩ずつ」、その積み重ねが将来の健康な毎日につながっていきます。
まとめ
帯状疱疹ワクチンが認知症リスク低減につながる可能性は、近年の研究によって新たに見出されつつあります。その背景には、帯状疱疹ウイルス再活性化による慢性的な神経炎症が認知機能に影響を及ぼすことがあり、ワクチン接種によりそのリスクが抑えられる可能性が示唆されているからです。今後、さらに研究が進むことで、認知症予防における帯状疱疹ワクチンの役割は一層明らかになっていくでしょう。
現時点では、帯状疱疹後神経痛の予防に加え、長期的には認知症リスク低減にもつながる可能性があると考えられており、脳の健康を守る手段のひとつとして接種を検討する意義は十分にあります。接種を迷われている方や対象年齢にあたる方は、一度かかりつけ医に相談し、ご自身の健康状態に応じてご検討いただくことをおすすめします。
当院でも帯状疱疹ワクチン接種を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。