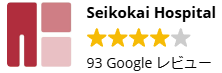健康診断や咳などの症状で医療機関を受診した際に、胸部レントゲン検査を受けた経験のある方も多いのではないでしょうか。
この検査は、肺や心臓、胸部の状態を確認するための基本的な検査で、日常的に広く行われています。そのため、多くの人にとっては比較的身近な検査といえるでしょう。
とはいえ、「異常があります」「影が写っています」といった結果を告げられると、やはり不安を感じるものです。
そこで今回は、胸部レントゲン検査で異常が見つかった場合に考えられる主な病気や、その後の受診や検査で注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。
不安を感じたときに役立つ情報として、ぜひ最後までお読みください。
まずは知っておきたい!胸部レントゲン検査の仕組みと特徴
 胸部レントゲン検査がどのようなものか知ることで、検査結果の理解にもつながります。まずは基本を押さえておきましょう。
胸部レントゲン検査がどのようなものか知ることで、検査結果の理解にもつながります。まずは基本を押さえておきましょう。
この検査は、肺や心臓、肋骨などの胸の内部の状態を画像で確認する検査です。X線を使って胸部全体を撮影し、肺炎や肺がん、心臓の大きさの変化、骨の異常などの有無を調べることができます。検査自体は短時間で痛みもなく、健康診断や体調不良時の初期診断として広く行われます。
気軽に受けられる検査ですが、レントゲンは平面の画像のため、すべての異常を完全に写し出せるわけではありません。
必要に応じてCT検査や超音波検査など、より詳しい検査を行うことがあります。
“異常”と診断されたら、やっぱり病気なの?
レントゲン検査では、肺の炎症やしこり(腫瘤)、心臓の大きさ、骨の状態などが写し出されます。
“異常”とは、あくまで画像上で通常とは異なる変化や影が見られたことを指します。
これは必ずしも重大な病気があるという意味ではなく、医師が、念のためさらに詳しく調べる必要があると判断した状態です。
たとえば、過去の炎症の跡や体格の特徴、検査時の姿勢や呼吸の違いによって、影が強調されることもありますので「異常=必ず病気」と慌てて結論づけるのは避けましょう。
“異常サイン”が示すものは?胸部レントゲンでわかる主な病気

では、胸部レントゲンで“異常”とされた場合、具体的にどのような病気や状態が考えられるのでしょうか。すべてが深刻なものではない一方で、見逃してはいけないサインもあります。
《代表的な病気や状態》
- 肺炎・気管支炎
肺の一部に炎症が起こる肺炎や気管支炎は、肺の影としてレントゲンに写ることがあり、その部分が白く濁って見えます。
発熱や咳、痰、胸の痛みなどの症状があり、風邪に似た症状から始まることも多いですが、急に悪化することもあります。 - 肺結核
肺の上の方に影が出たり、空洞(かどう)と呼ばれる特徴的な所見が見られることがあります。
結核菌による感染症で、長引く咳や痰、体重減少が特徴です。初期は小さな影として写ることがあります。 - 肺がん
小さな結節(しこり)が影として写り、異常影として見つかることがありますが、初期の段階では症状が現れにくく見つかりにくい場合もあります。
レントゲンで異常があった場合には、CT検査などによる精密検査を行い、がんの可能性を慎重に評価します。 - 心臓の異常(心拡大や心不全)
心臓が通常より大きく写る場合、心拡大や心不全の可能性があります。
息切れやむくみなどの症状がある場合は、心臓超音波検査(心エコー)などが行われることもあります。 - 胸膜や肺の周囲に起こる病気(胸水・気胸・胸膜炎・肺線維症など)
肺の外側を覆う「胸膜」やその周囲に異常があると、胸部レントゲンに異常が見つかることがあります。
たとえば、肺の周囲に液体がたまる「胸水」、空気が漏れて肺がしぼむ「気胸」、胸膜に炎症が起きる「胸膜炎」などが代表的です。
また、肺そのものが硬くなる「肺線維症」も、進行するとレントゲンに特徴的な影が見られます。
- 骨の異常(肋骨骨折や骨の変形)
レントゲンでは肋骨や脊椎などの骨も写ります。転倒や外傷後の骨折、あるいは変形や腫瘍などが見つかることもあります。
ただし、これはあくまでも一例ですので、焦らず医師の説明をしっかりと受け、必要に応じて追加検査などの対応を考えましょう。
「気になる影」と言われたら?3つのポイント
- 主治医の指示に従いましょう
「異常がある」と言われると、不安からすぐに別の医療機関を受診したくなるかもしれませんが、まずは現在の主治医の説明をよく聞き、指示に従いましょう。
医師は画像の内容やこれまでの診療情報を踏まえて、必要に応じて追加検査やCT、専門医への紹介などを判断します。慌てて自己判断をしてしまうと、かえって必要な検査や診断が遅れることにもつながりかねません。
- 症状の有無を正確に伝えましょう
レントゲンに異常が見つかっても、それだけで病気の診断が確定するわけではありません。実際に症状があるかどうかは、診断を進める上で重要な情報となります。
たとえば、咳が長引く、息切れを感じる、胸の痛みがある、痰に血が混じる、急激に体重が減少したなど症状がある場合は、画像の所見とあわせて、病気を見極める大きな手がかりになります。受診の際は、症状の始まった時期や変化の様子などをできるだけ具体的に伝えることが大切です。 - 定期的なフォローアップ
異常の種類によっては定期的に検査を受ける必要があります。
自己判断で「大丈夫だろう」と放置してしまうと、見逃してはいけない疾患が進行してしまうこともあります。必ず医師と相談し、指示されたタイミングで再検査や診察を受けるようにしましょう。
まとめ
 胸部レントゲンで「異常あり」と言われても、それがすぐに重い病気を意味するとは限りません。
胸部レントゲンで「異常あり」と言われても、それがすぐに重い病気を意味するとは限りません。
多くの場合は、追加の検査や医師の詳しい診察によって、より正確な原因がわかります。
不安なときこそ、ひとりで抱え込まず、まずは専門医に相談してみましょう。
当院では、最新のAI読影支援システムを導入し、AI読影支援システムと放射線専門医によるダブルチェック体制を敷くことで、高い診断能力をご提供しています。これにより、微細な異常も見逃さず、迅速かつ正確な診断が可能です。
また、検査後には結果をわかりやすく丁寧にご説明し、不安な点や疑問についても医師が親身に対応いたします。
安心して検査を受けていただける環境づくりを心がけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
早めの受診と正しい理解が、健康を守るための一歩につながります。